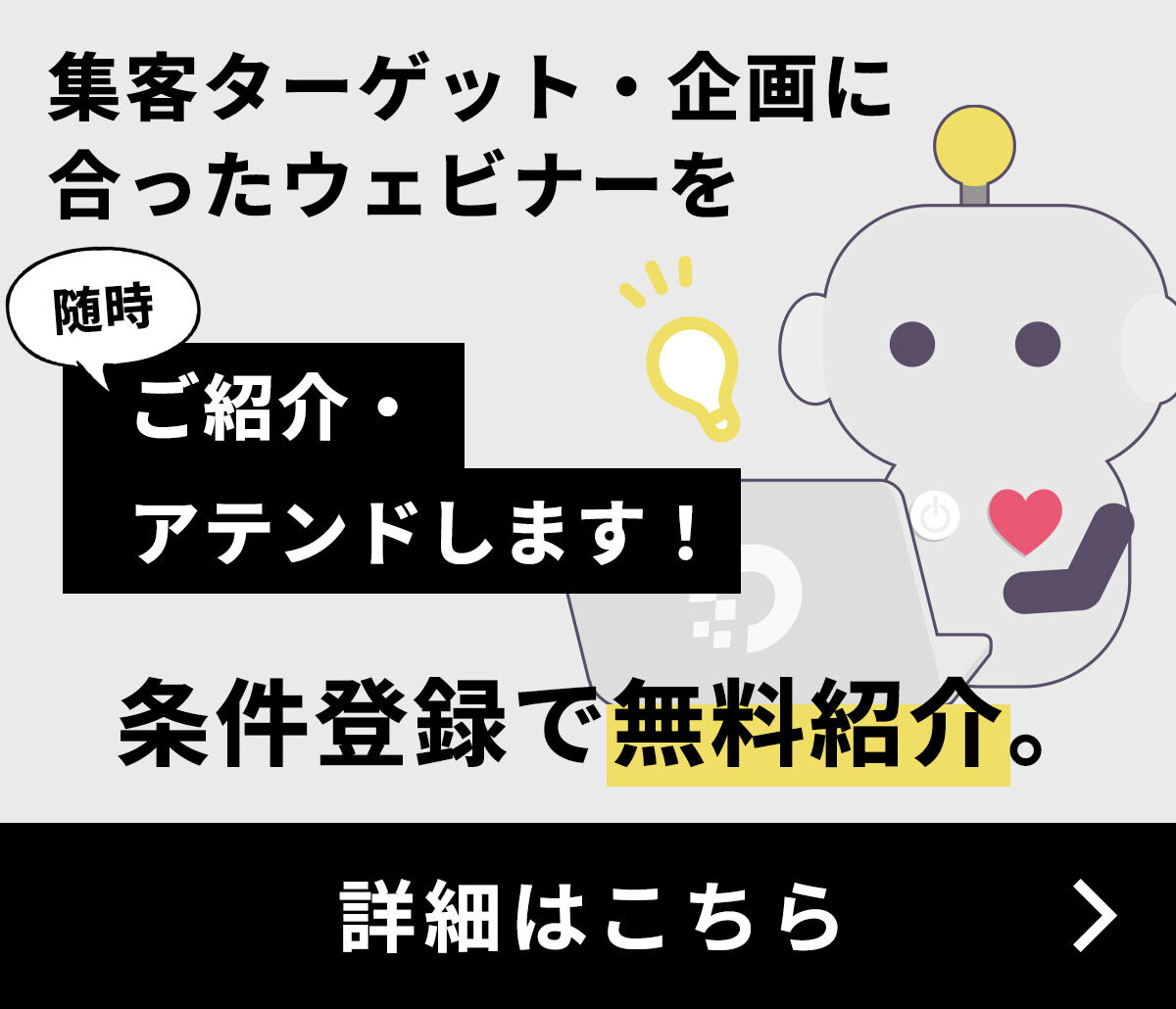
ウェビナー登録件数 1125
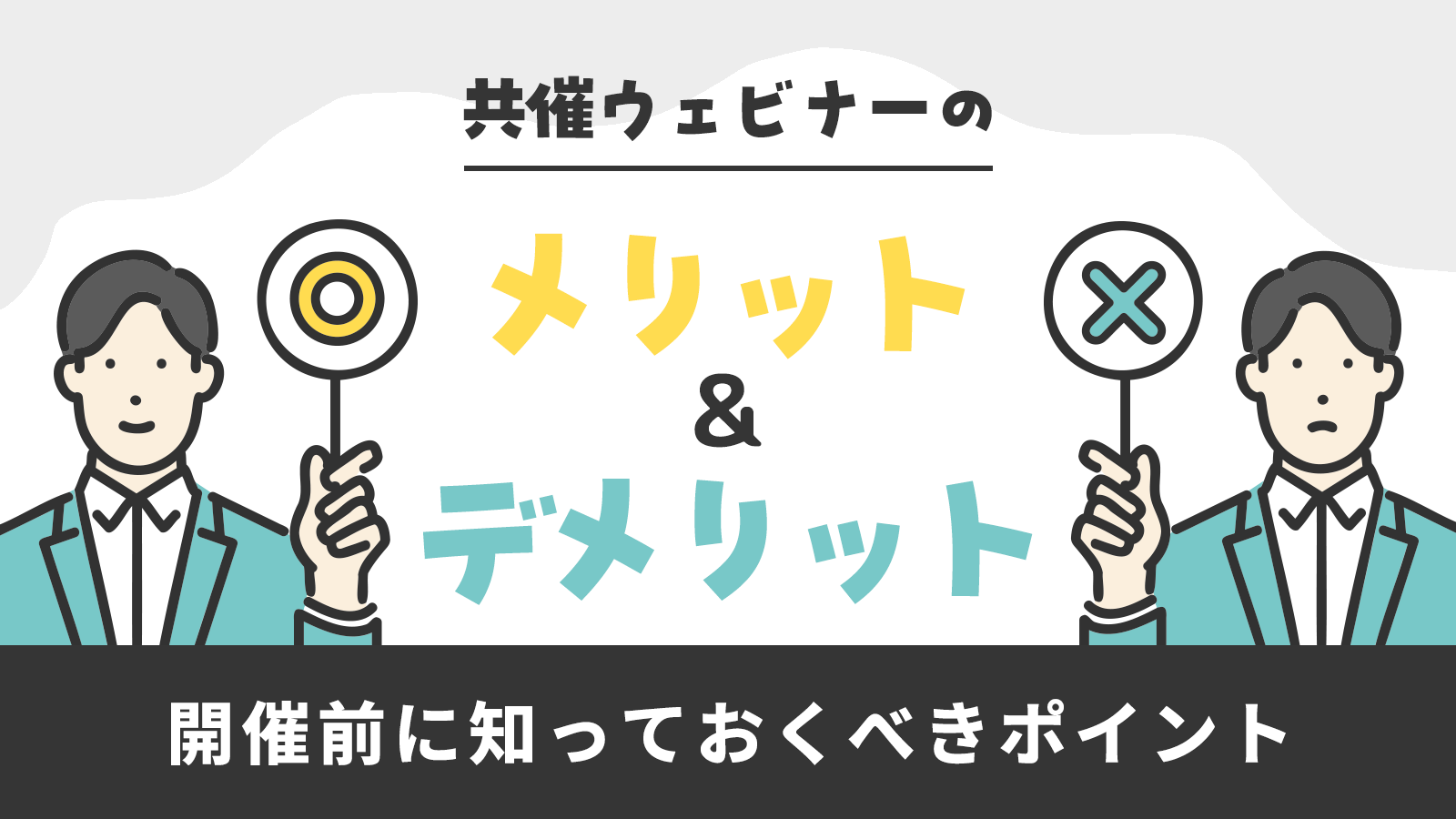
「共催セミナー、気になっていませんか?」
最近では、自社単独ではなく他社とタッグを組んで開催する“共催型セミナー”が注目されています。実際に、「今度のウェビナーは共催でやってみようか」という会話が、マーケティングや営業企画の現場で増えているのではないでしょうか。
しかし、いざやろうとすると、こんな不安が頭をよぎります。
そこで本記事では、共催セミナーを検討しているご担当者さま向けに、事前に知っておくべき「メリット」「デメリット」を整理し、成功させるためのポイントをわかりやすく解説します。
「共催の判断材料が欲しい」「上司に提案したい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
共催セミナーとは、複数の企業や団体が共同で企画・開催するセミナーを指します。1社単独での開催と異なり、それぞれが登壇や集客、コンテンツ制作などの役割を分担しながら、協力して実施するのが特徴です。
オンライン/オフライン、ウェビナー形式/リアルイベント問わず、形式は多様ですが、共通しているのは、「それぞれが持つ価値や顧客資産を掛け合わせて、より効果的なセミナーにする」という点です。
共催セミナーは、誰と組むかによって目的も伝え方も大きく変わります。単なる「枠の共有」ではなく、“補完関係”や“相乗効果”が生まれる相手と組むことで、成果に直結しやすくなります。
たとえば、
といったように、単独開催では難しい価値提供が可能になります。以下に、よくある共催パターンとその特徴を整理しました。
| 組み合わせ | 具体例 | 特徴 |
| SaaSベンダー × パートナー企業 | MAツール × 代理店 | 販売現場と提供元の視点がそろう。相互補完の関係。 |
| 類似サービス企業同士 | マーケティングSaaS × セールスSaaS | ターゲットが共通。顧客の課題を多角的にカバー可能。 |
| 事業会社 × 既存顧客(事例) | SaaS提供会社 × 導入企業 | ユーザー事例紹介を通じて説得力を強化できる。 |
| EC支援会社 × 決済・物流事業者 | EC構築ツール × 決済サービス/配送プラットフォーム | 店舗運営者向けに“売上拡大+運営効率化”の両面を訴求できる |
特にBtoB領域では、顧客の「課題解決プロセス」をテーマに据えると相性がよく、“単発の宣伝”を超えた価値提供型セミナーが組みやすくなります。たとえばEC業界では、
などの組み合わせは定番ですが、近年では、「楽天ECに強いコンサル会社」と「Amazon運用特化の支援会社」が共催し、モール横断型のEC戦略を語るといった“競合サービスの支援者同士”によるセミナーも増えています。
これは自社の支援領域に閉じないユーザー課題(例:複数モール併用)にフォーカスすることで、「比較検討している層」や「マルチ運用に課題を感じている層」に刺さるセミナーとして成立しているのです。
このように、一見ジャンルや立場が異なる企業同士でも、共通のターゲット課題さえあれば共催の可能性は広がります。
共催セミナーでつまずきやすいポイントのひとつが、「誰が何をどこまでやるか?」の曖昧さです。登壇者の調整や集客、配信環境、リード管理など、意外と多くのタスクがあるからこそ、事前に役割を明確に分担しておくことが、トラブル防止にもつながります。
以下は、共催セミナーでよくある分担パターンの一例です。
| 項目 | 担当例 | 補足ポイント |
| 集客 | 両社が保有リストにメール配信/SNS告知/広告出稿など | 「どちらが何件集めるか」「使用チャネルの重複」なども確認しておくと◎ |
| 登壇 | 両社から1名ずつ登壇、パネル形式もあり | 持ち時間や登壇順、テーマの重複に注意。内容のすり合わせが重要。 |
| 台本・スライド | 各社で分担 or 共同で1つの資料を作成 | 表現トーン・デザインルール・ロゴ掲載順などの調整が必要になることも。 |
| 配信・会場運営 | 主催側 or 両社協力(Zoom/Webinar配信、会場手配など) | 機材・接続環境の確認や進行スタッフの役割も含めて事前に詰めておく。 |
| 事後対応(リード管理・営業) | 登録情報を共有し、それぞれフォロー/あるいは分配方式を決める | 「誰がどこまで営業して良いか」「二重アプローチ防止」などは必ず取り決めを。 |
これらはあくまで一例ですが、最初のすり合わせをどれだけ丁寧にできるかで、共催セミナー全体のスムーズさ・成果が大きく変わります。
セミナー施策を検討する際、まず悩ましいのが、「単独でやるべきか?それとも誰かと組むべきか?」という選択です。共催セミナーには多くの魅力がある一方で、単独開催と比較したときの“向き不向き”もあります。
ここでは、実務上よく問題になる5つの観点から、両者の違いを整理してみましょう。
| 単独開催 | 共催開催 | |
| 集客リーチの範囲 | 自社の顧客リストやSNSフォロワーなど、自前のチャネルに限定される | パートナー企業の顧客リストや発信力も活用でき、集客の幅が広がる |
| コンテンツの厚み・説得力 | 自社の知見・事例のみで構成されるため、伝えられる情報に限りがある | 異なる視点や他社の事例が加わることで、説得力と深みが出る |
| 運営体制と負荷 | 企画・集客・登壇・事後対応すべてを自社だけで回す必要がある | 工数や役割を複数社で分担できるため、リソースが限られていても開催しやすい |
| 意思決定スピードと柔軟性 | スピーディに企画・実行でき、変更も即時対応可能 | 意思決定に時間がかかる。日程・内容の調整にはお互いの合意が必要 |
| リード活用と営業戦略 | 獲得リードはすべて自社で活用でき、営業方針も自社で完結 | リード共有ルールの取り決めが必要。二重接触や競合関係にも配慮が求められる |
単独開催と共催開催は、どちらが優れているという話ではありません。それぞれに強みと制約があり、セミナーの目的・対象・体制に応じて選ぶのがベストです。うまく組めば、自社単独では得られないリーチ・説得力・実行力を手に入れることができます。
次章では、なぜ今このタイミングで共催セミナーに注目が集まっているのか?を市場背景とともに紐解いていきます。
では、実際の現場では、どのような背景から共催セミナーが注目されているのでしょうか?
ここ数年、BtoBマーケティングの現場では、セミナー施策の内容や実施形式に変化が起きています。特に、従来の単独開催では届きにくかった層へのアプローチや、差別化の難しさが課題となる中で、「他社と連携してセミナーを行う」という選択肢に、現実的なニーズが集まりつつあるのです。
この章では、そうした共催セミナーが“今”選ばれるようになった理由や背景を、マーケティング施策全体のトレンドとあわせて整理していきます。
コロナ禍以降、BtoBマーケティングの主戦場は一気にオンラインへと移行しました。その結果、ウェビナー・LP・ホワイトペーパーといった施策が乱立し、「似たようなセミナーが多すぎて差別化できない」「集客しても伸び悩む」といった声が増えています。
この状況のなかで、他社との共催による“視点の新しさ”や“信頼の裏付け”が差別化要因として機能しはじめています。
単独開催では、自社の保有リストやSNSフォロワーが集客の主力ですが、リードの枯渇・既存リストの反応率低下という課題が避けられません。
共催セミナーは、お互いのリストを活用し合うことで「新しい層」にアプローチできる数少ない手段です。広告費をかけずに、ターゲットの幅を広げられる点でも、費用対効果の高い施策とされています。
情報収集行動の傾向として、ユーザーは「営業色の強い単独セミナー」よりも、複数の企業から話を聞ける比較型・事例型のセミナーを好む傾向があります。
特にBtoBの意思決定プロセスでは、複数サービスを横並びで比較検討するシーンが多く、 共催セミナーのほうが「偏りのない情報」を得られる場として支持されやすいのです。
近年は「とりあえずリード数を稼ぐ」時代から、「確度の高いリードを育成して、商談化につなげる」時代へとシフトしています。
その観点で見ると、登壇内容にリアルな顧客事例が含まれる共催セミナーは、信頼感・温度感が高まりやすいというメリットがあります。営業チームからの評価が高い理由のひとつです。
「共催セミナーをきっかけに提携が進んだ」「協業関係が自然に広がった」という声も多く、共催セミナーは単なるリード施策にとどまらず、企業間連携や“共創型マーケティング”の第一歩としても活用されています。
とくにスタートアップ・SaaS業界では、お互いの“売り先”や“提供価値”を補い合える関係性の可視化にもつながるため、 営業・マーケ・アライアンス部門の連携強化にも一役買っています。
セミナーがあふれ、ユーザーの目も厳しくなった今だからこそ、「誰と組むか」「どんな価値を共創するか」を意識したセミナーが選ばれる時代です。共催セミナーは、単なる“分担の仕組み”ではなく、今のBtoB施策における“戦略的パートナーシップ”の象徴とも言える存在。
次章では、そんな共催セミナーが持つ具体的なメリットをさらに掘り下げていきます。
ここでは、実際に共催セミナーを実施することで得られる代表的なメリットを5つに整理してご紹介します。それぞれ「なぜ効果が出るのか?」「どのようなケースで有効なのか?」という視点から解説していきます。
共催最大の魅力のひとつが、両社の持つ顧客リスト・発信チャネルを掛け合わせられることです。自社単独ではリーチできなかった層にもアプローチでき、結果として集客力が向上します。
特に以下のようなケースでは効果が顕著です。
無理に広告費をかけず、“リスト連携型”のローコスト集客が可能になります。
複数企業が同じ場で情報発信をすることで、参加者にとっては営業臭の少ない“中立的な場”に映りやすくなります。特に以下のような共催は、信頼形成に強く作用します。
「複数社が一緒にやっている=裏が取れている」という、心理的安心感を与える効果が期待できます。
1社単独のセミナーでは、自社製品や知見に限った内容になりがちですが、共催では異なる立場・視点を持つパートナーが加わることで、セミナー内容が立体的になります。たとえば、
このように視点が交差する設計にすることで、参加者の理解促進や満足度の向上にもつながります。
企画・登壇準備・集客・配信など、セミナーには多くの工数がかかります。共催であれば、業務を分担することで一人ひとりの負担が軽減され、結果的にクオリティ維持と実施回数の増加を両立しやすくなります。
など、運営体制を標準化することが成功のコツです。
意外と見落とされがちですが、共催セミナーはパートナー企業からの学びの場にもなります。
「自社の運営力を底上げする機会」としても共催は有効です。担当者同士の横のつながりができれば、次回以降の協業や提携にも発展する可能性もあります。
共催セミナーは、「人手が足りないから手伝ってもらう」という受け身の発想ではなく、“お互いの強みを掛け算して成果を高める”ための戦略的な手段として捉えるべき施策です。適切なパートナーと、適切なテーマで、適切な体制を組めば、1社単独では実現できなかった成果が見えてくるはずです。
次章では、そんな共催セミナーに潜む注意点やリスク=デメリットについても正しく理解しておきましょう。
共催セミナーは、企画・集客・登壇・フォローといったさまざまな工程を複数社で担う分、 「単独開催とは異なる工夫や気配り」が必要になります。
この章では、共催ならではの注意点と、それをスムーズに乗り越えるためのポイントを4つご紹介します。 あくまで“準備次第で回避可能なもの”ばかりですので、事前に知っておくことで安心して取り組めるはずです。
複数社で進めるからこそ、日程や内容の調整に一定の時間がかかるのは自然なことです。
といった場面もあります。対策としては、
など、プロジェクト運営の工夫でスムーズに乗り越えられます。
共催する企業によっては、発信スタイルや登壇トーンが自社と異なることもあります。たとえば、
といった点が生じやすいため、事前に以下のような確認が効果的です。
結果として、視聴者にとって統一感のあるセミナーが実現できます。
共催セミナーでは、得られた登録情報やリードをどう扱うか?が重要な論点です。企業によって営業方針や個人情報の扱いが異なるため、後から「思っていたのと違った」となるケースも。
以下のような事前確認が効果的です。
これらを明文化しておくだけで、お互いに安心して営業活動につなげられる体制が整います。
複数企業が登壇すると、それぞれの話にフォーカスが分散し、結果として「結局どんな話だったの?」という印象を持たれてしまうことも。
このようなブレを防ぐには、
これにより、視聴者にとってメッセージが明確で納得感のあるセミナーになります。
共催セミナーには、単独開催とは違った特性があります。だからこそ、事前のすり合わせや準備次第で成果に大きな差が出る施策でもあります。
本章で紹介した注意点は、裏を返せば「ここさえ押さえれば失敗しにくくなる」ポイントです。こうした設計を丁寧に行うことで、共催セミナーのメリットを“最大化”しながらリスクを最小化できるようになります。
次章では、「どんな企業・シーンに共催セミナーが向いているのか?」について具体的に見ていきましょう。
ここまでで、共催セミナーの特徴・メリット・注意点を把握してきました。では実際に、自社の状況や目的において“共催という選択肢が本当に適しているかどうか”はどう見極めればよいのでしょうか?
この章では、判断材料として使いやすい4つの視点から、向いているパターン/向いていないパターンを整理します。
共催がうまくいく条件のひとつは、お互いのターゲット層や顧客課題が近いことです。たとえば、同じような業種・職種をターゲットにしていたり、「複数サービスを比較している層」に向けて並列的な情報提供ができる場合は、共催の価値が発揮されやすくなります。
逆に、まったく違う市場を相手にしていたり、メッセージに一貫性を持たせにくいテーマだと、「誰向けのセミナーか分からない」という印象になりやすいので注意が必要です。
共催が単なる「人が多いだけのセミナー」になってしまうか、「おもしろい組み合わせ」として成立するかは、コンテンツの相性がカギです。
たとえば、「ツール提供企業 × 導入支援会社」「マーケター × セールスマネージャー」など、立場の違いを活かせる組み合わせなら、話の広がりや説得力も生まれます。
一方で、両者が似た内容を話す場合や、構成に補完性がない場合は、参加者にとって“冗長”な印象になりかねません。
共催は、進行や折衝、コンテンツ調整などに一定の調整スキルが求められる施策です。実務担当者がひとりで全部を抱え込むのは難しく、ある程度の推進力や他部門との連携力が必要になります。
少人数チームや初めてのセミナー開催でリソースに余裕がない場合は、セミナー運用支援を行うパートナー企業に舵をとってもらうのもいいでしょう。
意外と見落としがちですが、パートナー企業との関係性や価値観の相性も、共催の成否を大きく左右します。たとえば、すでに付き合いがある企業、信頼関係があるパートナー、普段から協業しているメディアや支援会社であれば、共催はスムーズに進みやすくなります。
反対に、「進め方の感覚が合わない」「トーンやメッセージにズレを感じる」といった場合は、無理に共催に踏み切るのではなく、一度持ち帰って再検討するのが賢明です。
このように、どれだけ事前に考えても、「共催が向いていたかどうか」は、やってみないと見えてこないことも多いです。だからこそ、テーマを絞ったショートセッションや、親しい企業との小規模共催など、スモールスタートで試してみることをおすすめします。
経験を通じて、「このタイプの会社とは組みやすい」「こういう進め方がうまくいく」といった知見がたまり、“共催の勘所”が自然と磨かれていくようになります。
共催セミナーは、単なる“工数の分担”ではありません。それはむしろ、マーケティング・営業・ブランディングの各側面で、自社だけでは到達できない価値を引き出す施策です。
ただし、共催は「やれば成果が出る」魔法のような手法ではありません。むしろ、事前のすり合わせ・役割分担・情報設計の巧拙が成果に直結する、繊細なマーケティング施策です。
こうした問いに、社内でも社外でも腹落ちする設計ができてはじめて、「やってよかった」と思えるセミナーが実現します。

