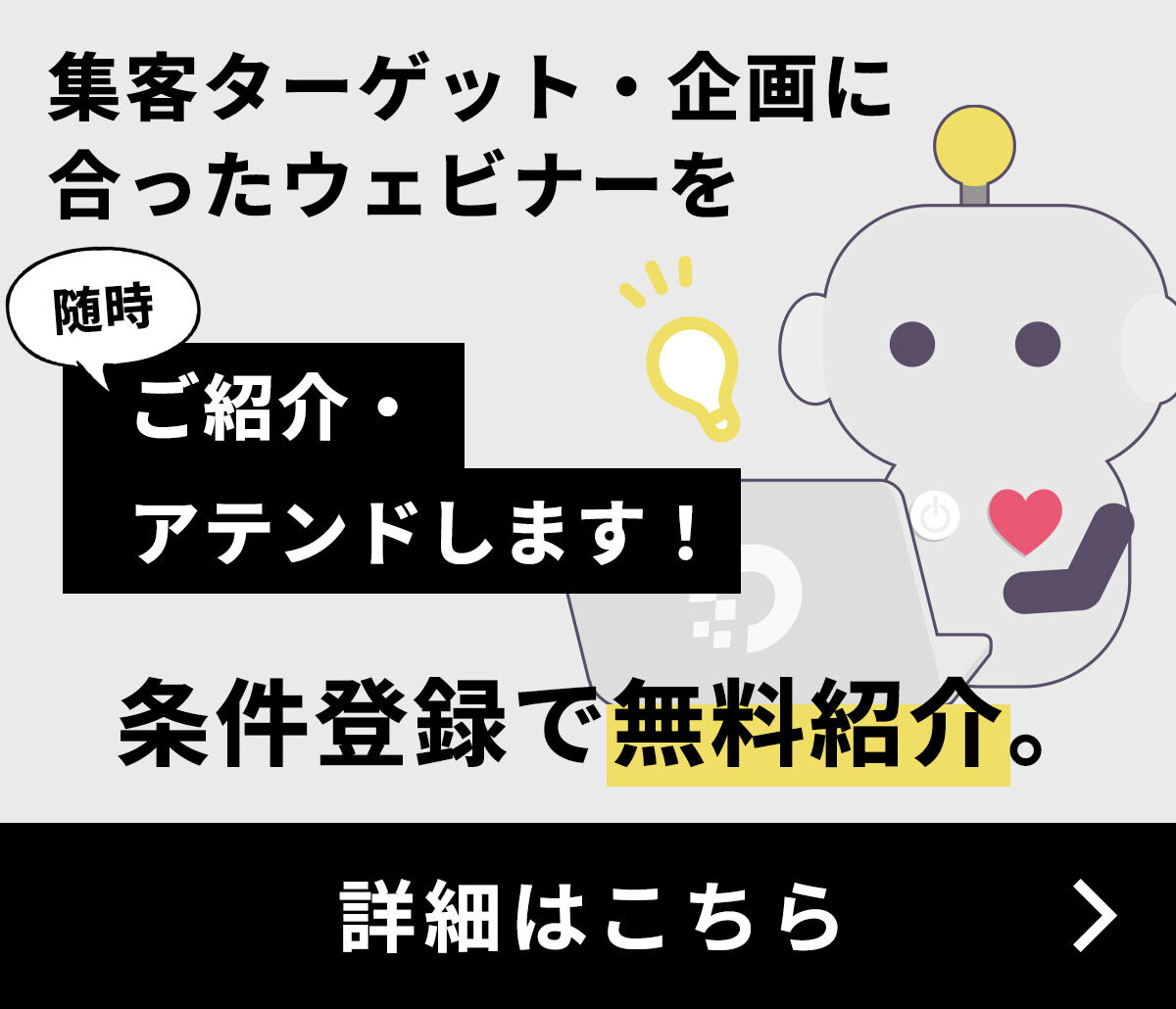
ウェビナー登録件数 1125
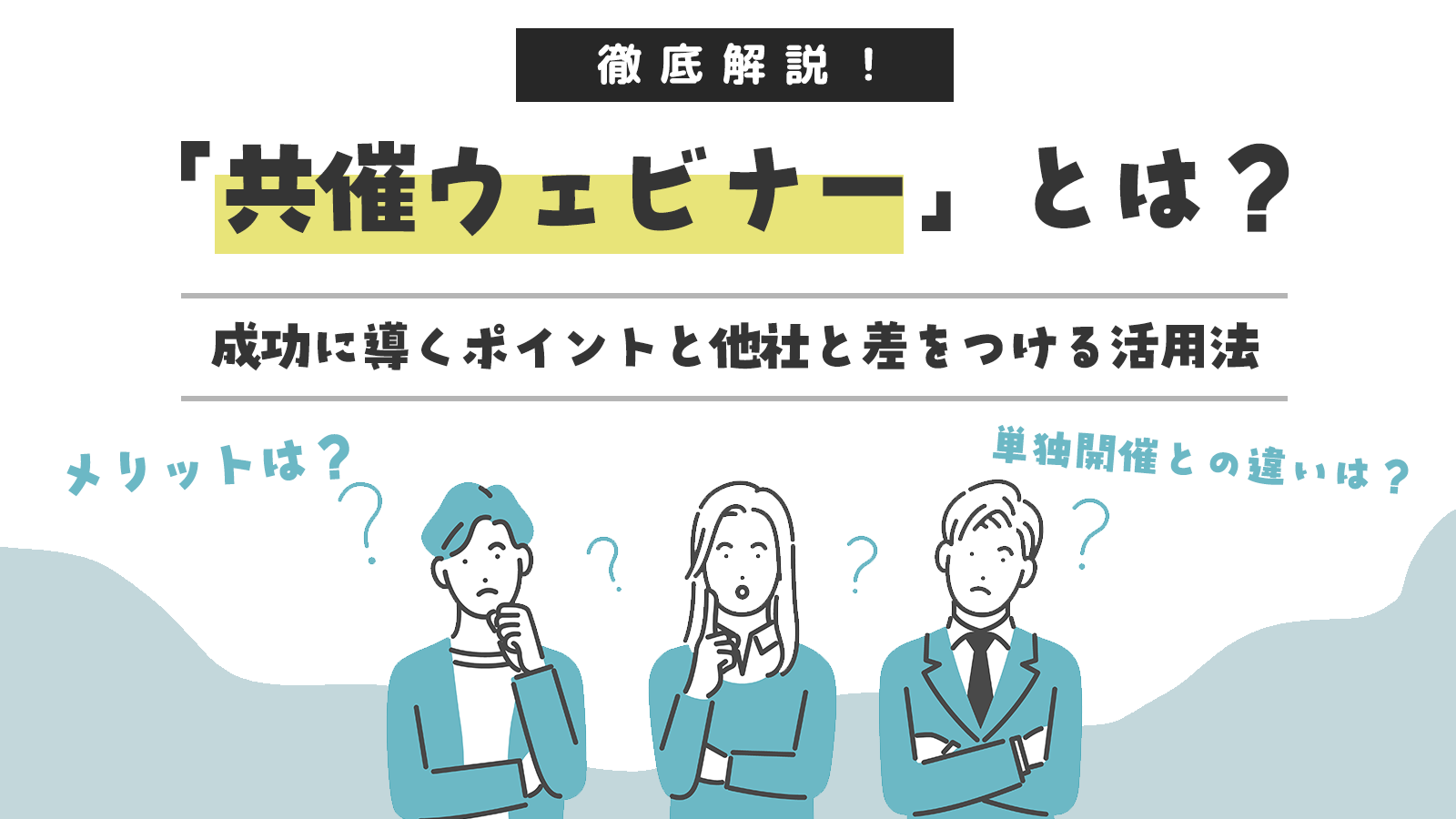
BtoBマーケティングの現場では、リード獲得や商談機会を創出する手段として「ウェビナー(Webセミナー、オンラインセミナー)」が定番になりつつあります。中でも最近注目されているのが、複数の企業が協力して開催する「共催セミナー(共催ウェビナー)」という形式です。
「セミナーを開きたいが、集客が不安」「初めての開催でリソースが足りない」といった悩みを抱える企業にとって、共催セミナーは魅力的な選択肢です。しかし、パートナー選びや役割分担でつまずくケースも少なくありません。
この記事では、共催ウェビナーの基礎から、成功のための実践ステップ、そして他社と差をつけるためのポイントまで、企画担当者目線で解説します。
共催ウェビナーとは、2社以上の企業が共同で企画・運営するオンラインセミナーです。
以下のような目的で活用されることが多くあります。
| 項目 | 単独セミナー | 共催セミナー |
|---|---|---|
| 費用負担 | 全額自社 | 分担可能 |
| 集客力 | 自社リストのみ | 複数社のリストで広がる |
| テーマ設計 | 自由度が高い | 合意形成が必要 |
| 運営負荷 | 全て自社で対応 | 分担できるが調整も発生 |
共催によって、自社がこれまで接点を持たなかった他社の顧客層にもアプローチが可能です。リードの質が高まるだけでなく、相互送客が期待できます。
複数社で実施することで、「信頼性」「客観性」が自然と醸成され、参加者に与える安心感もアップします。特に有名企業との共催はブランド強化にも繋がります。
コンテンツ作成、広報、当日の進行など、タスクを分担できるため、1社あたりの負担が減りやすいという利点もあります。
共催により複数の視点が交差することで、テーマに深みや広がりが出やすく、参加者満足度の高い内容を実現しやすくなります。
ケース1:責任の所在が曖昧 → 事前に役割を明確化
運営責任者やタイムラインをドキュメント化して明示しておきましょう。
ケース2:集客目標が共有されていない → 目標の共通認識
目標人数やターゲット層を事前に合意しておくことが大切です。
ケース3:ターゲットがズレる → ペルソナのすり合わせを
共通のペルソナ像を設定することで、内容がブレにくくなります。
ケース4:リード共有でもめる → 契約書で明確に取り決める
取得したリードの使い方については明文化された合意(NDAや個別契約)が必要です。
ステップ1:目的とターゲットのすり合わせ
ステップ2:共催パートナーの選定
ステップ3:企画・台本づくり
ステップ4:集客・告知分担
ステップ5:本番〜アフターフォロー
ウェビナーギャラリーでは、過去開催されたウェビナーを数百件以上掲載しています。
どのようなテーマで開催されているか、どのような企業が参画しているかを絞り込んで検索することも可能ですので、ウェビナーの企画にぜひお役立てください!
共催ウェビナーは、うまく活用すれば集客力・信頼性・コンテンツ力の相乗効果が得られる施策です。
一方で、パートナー選定や役割分担に失敗すると、運営トラブルやブランド毀損のリスクもあります。
ぜひ本記事を参考に、貴社の目的に合ったパートナーを見つけ、共催ウェビナーを成果につながる施策として活用してください。


